毎度です!大手前大学 通信教育部 アラフィフ社会人女子(⁈)大学生の森﨑さくらです。
1クール目の単位修得試験が終りましたね。
みなさま、おつかれさまでございました!
よく頑張られました!!!
しっかり、ご自分にご褒美をあげてくださいね。
私は、今回2科目だけでしたが、自分にご褒美をたーーっぷりあげました🍺笑
2科目のうちの一つが「調査研究方法Ⅰ」です。
心理学メジャーの修得ために受講しました。
昨年度、統計関係を頑張ったので勢いで・・・
成績はまだわかりませんが、5回から15回までを1日でするという離れ業(あかんやつ)をしました。
心理学統計法や心理学研究法を学んだあとだったので、とてもスムーズに進めることができました。(用語などが理解できたので)
先生の授業も分かりやすく、サクサク進めることが出来ました。
結局、朝から晩まで14時間以上勉強して、単位修得試験まで終わらせました。
燃え尽きましたよ。。。
大手前大学通信教育部の授業「調査研究方法Ⅰ」について、完全な主観、勝手な解釈でまとめた備忘録です。
「調査研究方法Ⅰ」データのウソの見極め方

「調査研究方法Ⅰ」は、3人の先生がオムニバス形式で授業を進めてくれます。
レベルナンバー:200
単位:2単位
メジャー:心理学/ビジネス・キャリア
単位修得試験:Web試験
資格名:社会調査士
「調査研究方法Ⅰ」を学ぶことで証拠として出しているデータが本当に正しく使われているか見極めることができます。
例えば、街頭インタビューなどで出されたデータを素に伝えているテレビに対して、データを鵜呑みにせず「どこで調査したものか?」「調査の対象者は?」「サンプルの抽出方法は?」と考えることで、巧妙に情報を操作しているのではないか?と疑問を持つことができます。
悪徳業者が、独自で取ったデータを元に騙して購入させようとしてきた時にも、データを利用した巧妙なウソを見抜くことができます。
以下のようなポイントを確認することができます
- データの信頼性: データがどのように収集されたのか、その方法が適切かどうかを判断します。データが信頼できるサンプルから収集されているかを確認することが重要です。
- バイアスの有無: データにバイアスが含まれていないかを見極めます。例えば、特定の地域や年齢層に偏ったサンプルが使われている場合、そのデータは全体の傾向を正確に反映していないかもしれません。
- データの分析方法: データがどのように分析されているかを理解します。数字だけでなく、その背景にある行動や反応を考慮することで、より正確な判断が可能になります。
正しいデータを集めようと思えば、国が5年ごとに行う「国勢調査」のように全員に調査できたらいいのですが、時間もお金もかかるのでなかなかできません。
そこで、サンプル数の決め方が重要になります。
サンプル数の決め方によって、データの信頼性が変わります。
全体を調べなくてもこれくらいの人にアンケートを取れば大丈夫なサンプル数があります。
以下の動画が分かりやすかったので見てみてください。
そして、95%信頼できるサンプル数はいくらなのか簡単に調べるサイトもありましたので、ご確認ください。
サンプル数が決まったら、偏りなくランダムに標本を集める方法が紹介されている動画もご覧ください。
【社会調査を行う心構え】協力者の時間を奪うからには誠意をもって調査を行い社会に公表すること
いかなる問題も社会的な問題と関連付けて調査すれば社会調査となります。
そして、調査するからには、キチンと調査結果を公表するまでが社会調査です。
今回の授業で、先生が繰り返し熱量をもって伝えられていたのは、調査に参加してくれる方の時間を奪うということです。
貴重な時間を割いて調査に協力していただくので、いい加減な準備ではいけないことを学びました。
少ない時間できっちり必要な情報を集められるように、しっかりと計画を立てて調査をしなければなりません。
そして、調査研究方法で最も大切なのは、貴重な時間を割いて調査に参加して下さる方に感謝であることを学びました。
感謝の気持ちを忘れなければ、調査準備もいい加減にはしないと思います。
アンケートなど多くの方々に調査をお願いする事は、相手にとっては迷惑であり、そのことをしっかりと肝に銘じていい加減な調査をしてはいけない。
また、ちゃんとせっかく協力いただいたアンケートが無駄になるような事は絶対にしてはならないと先生は強くおっしゃっています。
とても心に響きました。
いい加減なアンケートでいい加減な結果を出すと、それがあたかも本当のことであるようにデータとして残ってしまうため、社会に迷惑をかけることもあります。
なので集めたアンケートや調査書は必ず社会の役に立てなければなりません。
そうしなければアンケートに答えていただいた方の労力時間を無駄にしたことになるのです。
そんな事は絶対にしてはいけないと先生は熱く語ります。
その気持ちを持つことで、アンケートを取るまでの準備をしっかりすると思います。
1番大事である調査者の心構えを学んだ授業でした。
社会調査の代表的な調査方法は、「量的調査」と「質的調査」があります。
私の勝手な解釈で、「量的調査」と「質的調査」の2つをまとめていきます。
【質的調査】数値化できない調査方法です
質的調査には、聞き取り調査や参与観察法などがあります。
聞き取り調査の代表的なものは、インタビューがあります。
新聞や雑誌、インターネットでインタビュー記事がよく見られますね。
参与観察とは、調査対象の集団に入り込んで生活を共にしながら観察しデータを収集します。
参与観察をムツゴロウさんに例えて考えてみました

動物の生態を調べるために動物と行動を共にし、群れに入り研究調査を行うことは「参与観察」に該当すると思います。
例えば、ムツゴロウさんが犬の性格を調査する場合、犬と一緒に過ごし、観察します。
彼は犬がどのように遊ぶか、どのような反応を示すかをじっくり観察し、犬の性格や行動パターンを理解します。
時間をかけて犬と関わり、深く理解しようとします。これが質的調査です。
ムツゴロウさんは、ライオンやクマなど獰猛な動物の生態も理解し近づいて仲良くなります。
動物の中に入って行動パターンや感情などを調査しているのだと思います。
動物の中に入ってあたかも仲間であるかのように動物と接して動物を調査しているのです。
動物たちは、ムツゴロウに心を開き仲間としてムツゴロウさんに接することで、ムツゴロウさんは動物たちのより正確に生態を調査することができます。
【量的調査】数字を用いる調査方法です

量的調査とは、データや数字を使って物事を調査する方法です。アンケートや実験を行い、結果を数値で表します。そして、その数値を統計的に分析します。
たとえば、ムツゴロウ王国にいる100匹の犬について調査する場合、各犬の体重、身長、食事の量などを測り、データを収集します。
そして、そのデータを使って「平均的な犬の体重は何キロか」「どのくらいの量の食事を与えるべきか」を分析します。これが量的調査です。
調研究方法Ⅰのまとめ

調査研究方法を学ぶことで、このデータはどのように調査されたのだろう。などと考えることができるようになることで、簡単に騙されることがなくなるのではないでしょうか。
統計における「n」は、サンプルサイズを表します。つまり、調査や実験において実際に計測・収集したデータの数のことです。
たとえば、こちらのブログで私がお伝えしていることは、完全に私の主観であり、「n数は1」の感想なのです。
私一人がこの授業が面白かったよ。
おすすめですよ。
と伝えても、本当に面白いのかは、わかりません。
100人が面白いと言っているわけではないのです。
私の考えつまり、サンプルサイズは、「n=1」なのです。
こうして考えると、統計など調査方法で、サンプルサイズがいかに大切なのかが理解できます。
学生100人にアンケートを取るということは、サンプルサイズ100つまり「n=100」なのです。
私一人が、面白い授業というより、100人のうち90人が面白い授業と答えている方が説得力がありますね。
このことを悪用する人もいるのです。
なので、こうして世の中のデータを自分で正しいデータなのか見極める目を持つことは大切なことなのだと思いました。
1クールは、通常授業は2科目4単位しか受講していないのですが、スクーリングはめちゃ参加しています。
大学へ行くのは楽しいです。
お友達もできました。
短い学生生活、いっぱい学んで、いっぱい楽しみましょう。
いくつになっても今が一番若いのです。
今しかできないことに挑戦しましょう。。
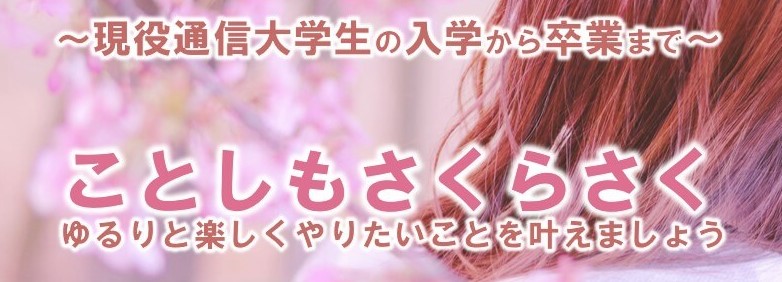
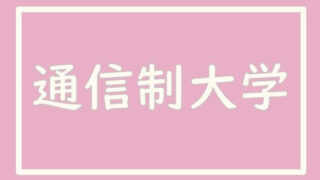






Chat Cafe 開店中
情報を得る時、その情報の発信元は?どのくらいのデータがあるの?など考えると、情報リテラシーが高まります。
いいねやレビューを購入できるなど、データをあかん方に利用することもできるので、ややこしいです。
私のブログは完全に個人の感想で、自己満足の世界なのですが、自身の勉強にもなるので卒業までは、続けようと思ってます💪
本を1冊読まないといけない授業…
それは、「精神分析学」
1回目から進まないのは、1回目の確認テストが、本を読んだ感想を書かないと行けないからです
2年前にできなかったのは、本が読めなかったからでした
また、とってしまったので、前に借りて読んでなかった同じ本を再び図書館で借りてきました…
今度は読めますよーに🙏